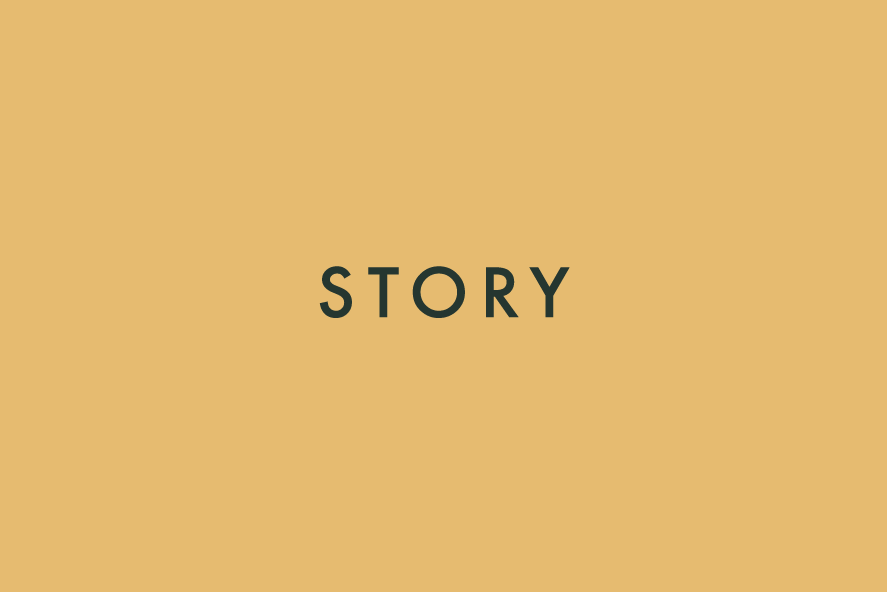
「さぁ、お茶の時間にしようか」
先生は、お昼過ぎになると決まって学生たちに声をかけ、研究室の隅に設置してあるお菓子BOXをゴソゴソとあさりだす。
もうきっと60歳をゆうに越えているだろうに、私の父よりもずっと若く見えるから不思議だ。いつだって子供のような瞳で、興味深く世の中を生きている。それが先生だ。
正直、お茶の時間なんて各自で勝手にやればいいと思っていた。
薬品の調合に真剣なときにおやつのことなんか考えてられないし、論文に追われているときにみんなでお茶飲みなんて、そんな悠長なことしてられない。
それなのにどうしたことか、お茶の時間になると、先生が陣取る大テーブルに足が向いている。
しかも、いつだかの飲み会でつい口がすべってしまい、実家が喫茶店であることがバレてからというもの、お茶の時間にコーヒーを淹れる担当になってしまった。
「やっぱりサラブレッドの淹れるコーヒーは格別だね」
なんて上機嫌に言われるが、淹れ方を教え込れたわけでもないので、絶対に気のせいだ。プラシーボ効果ってやつだ。
そう、先生はテキトー人間なのだ。
医薬品の研究でそこそこ名が知れているのに、まるで、その緻密で繊細な研究内容とのバランスを取るように、(面と向かっては言えないけれど)オフの状態ではちんちくりんである。
今日も、お茶の時間の小話がはじまった。
「その昔、世界で初めて病気が流行したときに、新薬の裏で生み出されたもの、それがお菓子だったんだ。知ってたかい?」
知らないというか、どう考えても嘘だけど、説得力がないわけでもなさそうだから面倒だ。
興味深そうに身を乗り出す友人の横で、ただ黙ってマグカップに口をつけた。
「病気そのものを治すには、もちろん薬が必要だ。でもね、そういう時期ってきっと何か良くないものが世に蔓延している。つまり、社会自体が病気にかかっているってこと。だとしたら、そこで生きてる人々も少なからず何かに侵されている。でも、病気になっていないうちから薬を飲むのもおかしな話でしょ?あ、おかしだけにね」
たまたま思いついたダジャレが口をついて出てしまうあたり、おじさんだな。
「だからね、僕が推測するに、毒にも薬にもならないものとして、この世にお菓子が生まれたんだよ。これ、おいしいね」
パイ生地のお菓子をバリバリと頬張りながら、紺色のセーターを屑だらけにしている先生を見て、思わず笑ってしまった。
「毒にも薬にもならないからといって、侮っちゃいけないよ」
とか言っている先生のウインクはちょっと腹立たしかったけれど、確かに、毒にも薬にもならないこの時間に、私も救われているのかもしれないと思った。
文=山越栞

