


20XX年2月1日、またチョコレート税法が改正された。今回の値上げで、3回目らしい。
お母さんはロボットから流れてくるニュースキャスターの声を聞きながら、キッチンでネギを切っている。奥にある鍋からは湯気が立ちのぼり、5分前にセットしたコードレスのホットクックからピピロロピロロと電子音が鳴る。
ぼくがダイニングテーブルをアルコールの除菌シートでふいて、ごはんとおかずをよそう。
お母さんはお味噌汁を運びながら「昔は板チョコも1枚100円だったのに」と嘆いた。
増税がなくても、ぼくたちの知っているチョコレートは高級だった。
「ひと昔前はね」それがどれほどの長さかは分からないけれど、お母さんが子どもだったころの話だと言うのだから本当に昔のことだ。
お母さんから聞くところによると、チョコレートはコンビニやスーパーマーケットのお菓子売り場の中で、かなりの割合を占めていたらしい。十数円で買えるものもあれば、ビスケットにチョコがかかったもの、ウェハースにチョコが挟まったものなど、さまざまなチョコレート加工菓子があったそうだ。
コンビニでは毎週新商品が発売され、バレンタインの時期には日本中のチョコレートがひとつの会場に集まり、平日でも何千人もの来場者が押し寄せた。
それくらい、チョコレートはいつの時代もひとを動かす力があった。
今ぼくらが買おうとしても、認可を受けている数少ないチョコレート専門店でしか手に入らない。さらにマイナンバーカードと購入履歴が紐づいていたため、買える量が制限されている。
先週、隣町の歯医者さんへ行った帰り道で、新しくできたチョコレート専門店を見つけた。車を運転するお母さんが先に気づき、「でもあそこ、認可受けてないのよね」とスピードを落とさず通り過ぎた。
「何で知ってるの?」
「こないだパートの山村さんからもらって食べたの。なんかねえ、チョコレートっぽいんだけど味がやっぱり違って」
それは生乳と乳飲料くらい違うと続けていたけれど、ぼくにはよく分からなかった。
「にせものってこと?」
「うーん、カレーが食べたい日の晩ごはんにカレーピラフが出てきたときって感じかな」
そう言って右のウィンカーを点滅させ、車線を切り替えた。
カレーピラフにはぼくの好きなコーンが入っている。どっちも嬉しいけどな、と思いながら車の窓から外を見ると、隣の車線で小型のソーラーカーを走らせている男のひとが板チョコレートをかじりながら運転している。包装紙には、さっき見つけたお店のロゴが描かれていた。
カカオに新たな栄養成分が見つかり、新薬開発のため市場に出回る量が制限されたのは9年前。ぼくが生まれた年のことだった。
たくさんのひとに愛されてきたチョコレートは今までのように購入できなくなり、もちろん反発や暴動が世界各地で起こった。
特に、チョコレートの自動販売機が街のあちこちにあるくらい市民にとって身近な存在だったイギリスでは戦争状態だったと言う。
日本も例外ではなかったらしい。ニュースの報道直後、ありとあらゆるチョコレート売り場はすっからかんになり、毎日のように国会前ではチョコレート税法案に対するデモが行われていた。
チョコレートを何としてでも手に入れようとするひとびとを出し抜くように高値で販売する悪徳業者が横行し、かつてカカオが貨幣だった16世紀に現代が逆戻りしていると話題になった。
「我が国では来年からチョコレート税を導入する。チョコレート国際法に則った税法を定め、政府から認可を受けた販売店のみ売買を行うよう、整備をしていく」
当時の総理大臣の会見はすべてのチャンネルで緊急速報として報道され、翌年の9月18日にチョコレート税法が導入された。
お母さんは、あまりにも唐突に政府によって世の中が変えられてしまうことに憤慨し、次の市議選に立候補したそうだ。
やろうと思い立ったら、何でもすぐに行動に移してしまうお母さんのことだから、きっと嘘ではないだろう。
結局900票ちょっとを集めて落選してしまったそうだが、選挙運動中にお父さんと知り合ったということはぼくにとっても結果オーライだ。もし当選していたら、市議会議員としてしばらくは忙しく過ごしていたかもしれない。
今朝のニュースは税法改正の話題で持ちきりで、朝ごはんを食べていても何となく舌の奥にチョコレートの味がする気がした。
時計を見ると、すっかり家を出る時間になっている。慌てて食器を重ね、「ごちそうさまでした」と言いながら流しへ置いた。
バッグをつかもうとすると、ノートと教科書代わりのタブレットが入っていないことに気づく。視線をあちこちへ飛ばすと、ダイニングテーブルの下に端末の角が見えた。
「別に遅刻したっていいんじゃない。人生長いんだし」のんきな台詞に似合わず、お母さんは眉間にしわを寄せながらニュースを見ていた。
画面の奥で話すコメンテーターが「この調子じゃまた数年以内に税の値上げがありそうですよね」と渋い顔をしている。
お母さんは、また選挙に出るんだろうか。
—
いつも通りの朝だった。7:32のバスに乗り、学校の前のバス停で降りる。下駄箱で上履きを取り出し、階段で2階までのぼる。なんとなく廊下がざわざわしている気がしたけれど、毎朝こんな感じだったはずだ。
教室に着き、自分の席に向かおうとすると「沢木、知ってる?」とぼくのふたつ前に座る内山が興奮ぎみに声をかけてきた。
またどうせゲームの話だろうとバッグを机の上に置き、上着を脱ぎながらどうしたのと聞いてみると「石井先生のことだよ」と急かすようにぼくの答えを待っていた。ぼくらの担任の先生だ。
石井先生は優しく見た目も小綺麗で、男女問わず生徒から人気を集めている。奥二重で薄茶色の瞳に、一本の筆ですっと描いたような整った眉毛、短く切りそろえられている黒くて細い髪。いつもスーツの中に着ているモスグリーンのセーターが、彼をより品良く見せていた。
「去年のバレンタイン、職員室の机いっぱいにチョコがあったらしいぜ」
「石井先生、モテそうだもんな」
「おれにいい作戦がある」
内山は腕を組みながらいたずらな目をしてぼくを見た。彼は、悪だくみをするのが好きだ。
「盗むのを手伝うんだったらやだよ」
「そんなバカなことはしないって。頭を使うんだよ」
そう言ってぼくにタブレットのメモ帳を起動させ、タッチペンで「チョコレートさくせん」と書いた。
バレンタインまであと2週間あまりだった。朝の会へ先生が時間ぴったりに来ることを見越して、ぼくと内山は8時15分ごろから教壇の周辺を掃除する。先生がドアを引いた瞬間には席にいないとまずいので、5分前から掃除用具を片付け始めた。
席へ着くとちょうどチャイムが鳴り、石井先生が予想通り定刻に入り口のドアを開ける。
「おお、今日は何だか教室がいつもよりきれいですね」
にこにこと笑みを浮かべながら脇に抱えていた日誌やPCを机に置いて出欠をとる。
最初の作戦は成功だった。
そのあともぼくらは先生が職員室に授業で使った資料を持っていこうとするのを手伝ったり、いつもより積極的に授業で手を挙げたりした。給食に苦手なニンジンが出てきても残さず食べた。
「最近ふたりにはすごく助けられている。毎朝掃除してくれているのも知っているよ。どうもありがとう」
ある日の放課後、いつものように内山とぼくが先生が荷物を職員室まで運ぼうとするのを手伝っていた時、先生は言った。バレンタインの、前日だった。
ぼくらはもう、チョコレート欲しさに良い行いをしているわけではなくなっていた。
困っている誰かを助けて感謝をされたり、やりたくないと思ったことをやってみるとそんなに大変じゃなかったりして、何だかそれだけでいい気がしてしまっていたのだ。
「先生」
内山は両腕に抱える資料に目線を落としている。彼も、もう嘘をつき続けたくなかったのかもしれない。
「実はおれ、良いことしてたらチョコレートを分けてもらえるんじゃないかと思ったんです」
「うーん。先生もらったことあんまりないからな」
「え?」
「でも去年いっぱいもらったんじゃ……」
内山より先にぼくの方が大きい声で驚く。
「そういうことか。じゃあぼくの机まで来てごらん」
そう言って先生は自分の机まで案内してくれた。机には、いくつものチョコレートの箱や缶がつまれている。
石井先生の奥さんが大のチョコレート好きで、捨てずにとっておいているらしい。家では使い途もないからと、先生がしぶしぶ学校で活用するようになったそうだ。
さらに、先生は甘いものが苦手だった。それを周りは知っているからか、もらうこともほとんどないと言う。
真実を知ると、ぼくらふたりは顔を見合わせて笑った。
—
職員室を出ると内山は「おれら、ただ良いことしてただけだね」とばつの悪そうな顔でぼくを見た。
「でも、先生が朝の掃除にも気づいてくれてたの嬉しかったな」
普段より少し早く起きなければいけないのは大変だったけれど、掃除をしていると朝からすっきりした気分で過ごせていたのだ。
「たしかに。良いことも悪いことも、ちゃんと誰かが見てくれてるのかもしれない」
ずるさをしているような後ろめたい気持ちから解放されたからか、安心したようにそのあとは最近やっているゲームの話をえんえんと聞かされた。
家へ着きリビングへバッグを置きに行くと、青い包装紙に赤いリボンがかけられた箱がダイニングテーブルの上にあった。
トイレから出てきたお母さんに尋ねると「最近良い子にしてたでしょ。一日早いけど」とぼくの前に差し出した。
細いリボンの端をひっぱり、包装紙のテープをていねいにぺりぺりと剥がす。
中から現れてきたのは、見覚えのある缶だった。そうだ、石井先生の机にあったものと似ている。
ひとつだけ違うところがあるとしたら、缶のふたに英語が書かれている。「これなんて読むの?」とお母さんに聞いてみると「ハッピーバレンタインよ」と言いながらぼくの頭をくしゃっとした。
お礼を言い、いちばん丸くてつややかな一粒に手を伸ばす。
口の中に放り込むと甘く、なめらかな食感が舌を覆う。
「チョコレートってほんとうにおいしいね」
「そうでしょう」
チョコレート税のことはまだ理解できない。だけど、この宝石のような美しい一粒のためにお母さんが戦おうと思った気持ちは、少しだけぼくにも分かるかもしれない。
「お母さんも一個食べていい?」
そう言って、マーブル色になっているひとつをぱくっと食べる。
チョコレートを頬張るお母さんの横顔は、とてもしあわせそうだった。
参考文献:
武田尚子(2010)『チョコレートの世界史ー近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石 』 中央公論新社.
ソフィー,D,コウ・マイケル,D,コウ(2017)『チョコレートの歴史』( 樋口幸子訳 )河出書房新社.
文=ひらいめぐみ 編集=スナックミー編集部
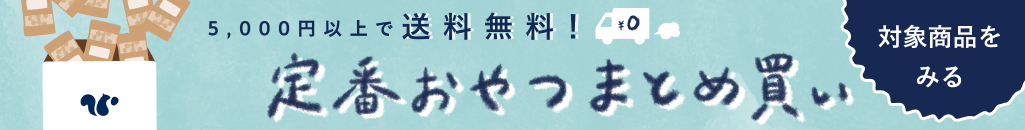
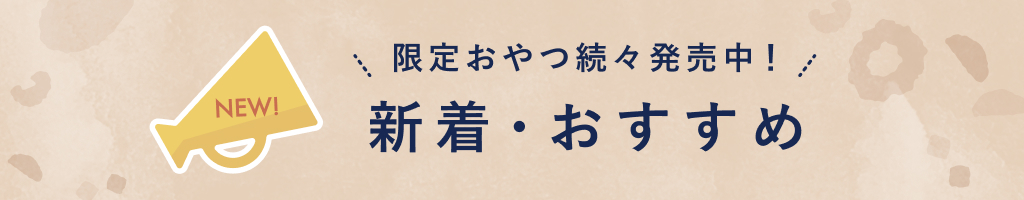
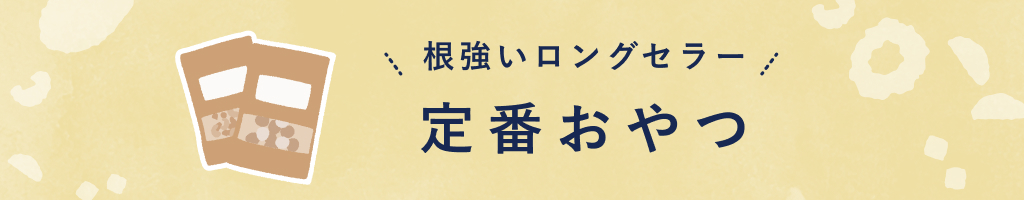
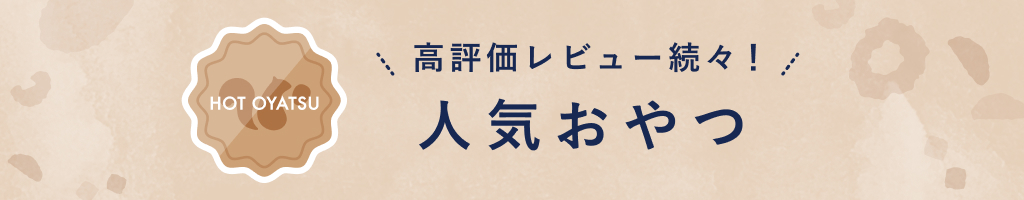
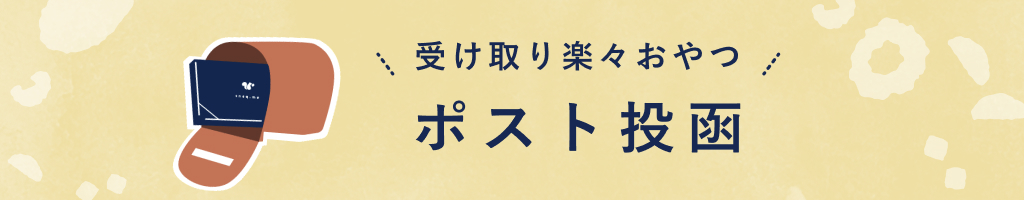

最新のよみもの
-

スナックミーの復刻おやつ特集🐿️
スナックミーは、今まで沢山の製造者様とおやつを作ってきました。おいしく仕上がっていたけれども泣く泣く販売がストップしてしまったものもあります。今回の特集では、過去に支持いただいていた人気のおやつをまたお届けできるようにしましたのでご紹介させていただきます。
-

春を先取る彩りおやつ特集🍓🌷
先週は東京にも雪が積もった驚きの週でしたが、2月に入りだんだんと春が近づいてきましたね。 スナックミーでは少し春を先取りして、彩りのあるおやつをご紹介します!
-

チョコおやつ特集 第二弾🍫
バレンタインも近づき、チョコレートおやつやバレンタイン限定イベントを沢山目にするようになりましたね。 スナックミーでも寒い冬の時期は沢山のチョコおやつを販売中・リクエスト受付中で、チョコおやつ特集第一段ではすべてをご紹介できなかったので、今回はチョコおやつ特集第二弾です! 自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントにいかがですか?



