


さくり、さくりとハサミが動く音を聞きながら、足元に落ちる長い髪の束を見つめる。「すみません、もう少し上を向いてくださいね」と首を上に向けられる。
美容院へ行くのは1年ぶりだった。何年もロングヘアで、肩より下までいくと、どれだけ伸びてもあまり気にならなかった。
初めてのブリーチに、電気が走るような痛みが刺す。
染みてますか?と聞かれても、何をもって「染みている」状態か分からない。
大丈夫です、と発した自分の声が頼りなく響く。液剤がどんどん頭皮に広がっていくのを感じ、ようやくもう後には戻れないと気づいた。
次の日職場に行ったらぎょっとされたけど、次第に周りも見慣れていったようだ。数週間もすると誰にも何も言われなくなった。
6年前、初めて文学賞に応募した。五大文芸誌の新人賞のような大舞台ではなく、4,000字以内のショートショートを募るものだった。
大学生活で初めての長い長い夏休みで、最初は浮かれていたものの、だんだんやることもなくなり、刺激のない日々が流れていく。海外にでも行ければよかったが、まだバイトを初めてまもないので貯金もない。
旅行に行けないなら、せめて物語の中で旅をしよう。そうしてひと夏で書き上げた短編小説が意外にも満足いく出来だったので、そのまま応募できそうな賞を探し、送信ボタンを押したのだった。
ひとつの物語を完成させたことですっかり応募したことも忘れていた翌年の冬、一本の電話がかかってきた。
大賞受賞の連絡だった。
その後のことはあまり覚えていない。
早生まれだったわたしは受賞時、ぎりぎりの十代で、『早咲きの新人作家』として良くも悪くもメディアから注目を浴びた。
慣れない取材に受け答える日々が続き、知人しか繋がっていなかったtwitterのアカウントは2,3日であっという間に数千人にフォローされるようになった。
発した言葉すべてに、意味という尾ひれがひらひらとつきまとう。言葉の海に一人溺れていく感覚だった。自分を自由にしてくれていた「言葉」という存在が、いつのまにか前へ進もうと動かす手足に絡みつき、ずぶずぶと光の届かない海底へ引きずり込んでいく。
応募前にふとツイートしていた短歌までも『この頃からすでに才能の芽は出ていた』などとまとめ記事で言及されるようになる頃には、読んだ直後、胃がむかむかして嘔吐してしまうようになった。
当然、期待されていた次の作品を書けるはずもなく、ほとんど大学にも通えないまま2年が経った。
大手の広告代理店、外資系の製薬会社に、グローバルに展開するアニメーション企業。
名だたる有名な企業が集まるこのビル内の唯一のコンビニでは、朝はコーヒーを受け取るひとで列ができ、昼はお弁当の温め待ちのひとでカウンターの前が溢れかえる。
オフィス街にあるこの場所なら、大学の同級生が来ることもない。
時給も良かったし、時々感じの悪いお客さんもいたがごく稀で、先月髪を金色に染めてからは変な絡み方をするひともいなくなった。
入り口正面の壁は全面ガラスに覆われており、日の光が燦々と降り注ぐ。外の景色は灰色の立ち並ぶオフィス街だったけれど、なぜだかとても気持ちのいい場所だった。
居心地の良さに甘えて何年も働いていると、次第に心身も回復していった。しかし就活になるとわずかなプライドが邪魔をして思うようにいかず、周りより一年遅れてなんとか大学を卒業した後も、わたしはコンビニのカウンターに立っていた。
これでいいんだ、と思った。
これがいいんだ、と言い聞かせた。
もう二度と書かない、と思いながらも「どこかでまた書けるだろう」という未練がましい気持ちがある。
ふと、指の隙間からすり抜けて落ちてしまう気がして、開いていた手をきつく結ぶ。
何もない日常がいい。「自分には才能がない」と気づかされる方が、よっぽど幸せだったのかもしれない。
朝はいつも、8時から始まる。買われるものの多くはコーヒー、栄養ドリンク、朝ごはん用のおむすび、サンドイッチ。半分くらいは毎日見かける顔ぶれだった。
似たようなものを売って、同じ人に毎日接客する。最初のうちはすぐ飽きてしまいそうだと思った。
ところが、それが良かった。
一定のリズムができてくると、日常はなめらかになることを知る。
今日もこのままピークが落ち着いてくだろう、と一息ついているときだった。
目の前に並ぶ男性の、見覚えのある顔にドキッとする。
スーツを着ていることで記憶の中との印象にかなり乖離があったが、おそらく高校の同級生だった。クラスも違っていたので、相手はわたしのことを認識していないかもしれない。それくらいの関係だった。
5つのレジがあるうち、自分の前が最初に空いてしまう。
名札の苗字に気づかれないよう、少しかがみながらサンドイッチのバーコードを読み取る。
名前は思い出せなかった。ただ、180cmを超えるくらいの身長と、「袋はいいです」の低い声に、やっぱりそうだろう、と確信した。
お昼のピークをこなすとあっという間に14時だった。窓のない、空気の淀んだバックヤードに入り、歯ごたえのないパスタを食べる。惨めだった。
どこで間違えてしまったんだろうか。
プラスチックのフォークに巻きついたパスタが、ひゅるりとほどけて器に落ちる。
きっと彼は大学を卒業してすぐに、このビルのどこかの会社に新卒で入ったに違いない。
だとしたら、絶対に競争率の高いこのビルのどこかの大企業で、仮に転職をしたとしても、これからの人生は、わたしよりずっと安定している環境で過ごすのだろう。
毎日毎日、お弁当を温め続ける人生。
このふにゃふにゃのパスタと同じように、明日も明後日も今の暮らしに抵抗することなく過ごしていくんだろう。
バックヤードを出て窓から外を見ると、さっきまで明るかった空を、分厚い雲が覆い尽くしていた。
昼間の出来事があってから、何となく頰に火照りが残る。
あとで計ったら平熱だったが、まるで負荷をかけすぎたパソコンのようにからだじゅうが熱を帯びていた。
家に着き、マフラーを外す。
まだ少しだけ残っている火照りが冷めないように、あったかいお茶をいれて、帰りに買ったどら焼きを横に置く。
PCを開き、真っ白なドキュメントを開いた。
何も書かれていないページはまるで誰も歩いていない雪景色のようで、文字を少しずつ打ち込んでいくうちに、もともとあった絵が浮かんでくるような不思議さがあった。
正確には、文字を連ねることで一つの絵ができていくはずだったが、彫り師のように無駄なものをそぎ落とすことで作品の輪郭をつくっていく、そんな感覚だった。
夢中になってPCに向かっていたらあっという間にマグカップは冷えていて、時計は2時を回っていた。
急にお腹が空き、手をつけていなかったどら焼きを急いで頬張る。ふかふかの生地にしっとりしたつぶあんが挟まれていて、柔らかい甘みが広がった。
大学1年の夏休みのときのような手応えはない。
だけど、すこんと長年の憑き物が取れたような清々しさがあった。
気づけば変な熱っぽさもひゅるひゅると萎んでいる。打ち上がったあとの花火ってこんな感じなのかな、と思いながら冷たい布団に入り込んだ。
翌朝、いつもより短い睡眠時間にもかかわらず、ぱっと目が覚める。まだバイトに行くには早い時間だったので、昨日のショートショートを匿名ブログに投稿した。
名前も素性も分からないこの場所でなら、誰もわたしがわたしだとは分からない。寂しいけれど、悲しくはなかった。
いつも通り仕事をして、定時ぴったりに打刻をした。17時でも外は暗く、まだまだ冬の最中にいることを知る。
休憩中、いつも欠かさず見ていたSNSを開いていなかったことに気づき、半日ぶりにアプリを立ち上げる。ふと、ブログをシェアする投稿が流れてきて、慌ててURLで検索をする。
シェアしているのは、ひとりではなかった。
明け方に書いた短い物語が、予想しなかったスピードで多くの人に広がり、読まれている。
匿名でアップしたので当然SNSの通知欄で気づくことはなく、まるで遠くの海が燃えている様子を反対岸から見ているようだった。
「燃えている」と言えど、炎上しているわけではない。ただ、早く鎮火してほしかった。注目されることで、これから起こる起承転結が見えているからだ。
スマホをホーム画面に戻し、音楽配信のアプリを開いて聞いたことのないアーティストの名前をタッチする。
違う自分になりたい。結局同じところに戻ってきてしまった気がした。
ひとつの曲が終わるやいなや、ぶるっとスマホが震えた。さっきまで開いていたアプリの、ダイレクトメッセージの通知がきている。
おそるおそる開いてみると、以前「二作目を書いて本を出しましょう」と連絡をくれた、とある出版社の編集者の方からだった。
<何で主人公は最後シャッターを切らなかったんでしょうね。>
たった一行のメッセージ。
昨日書いたショートショートの結末についてだった。
きっと、彼は誰が書いたのかを見抜いたのだろう。
誰にも気付かれなくていい、と思っていた。
でも本当は違っていた。
誰にも見られたくなければ、最初から公開しなければいいのだ。
—
日曜日、高校の同級生のユタカくんから急に遊ぼうと連絡があった。
進学を悩んだ末、今年の春に就職をした彼と会うのはちょうど一年ぶりで、髪がちょっと短くなったこと以外はさほど変わらない様子だった。
「仕事はどう?」と聞くと「つまんね」とユタカくんは渋い顔をし、「横田は変わらないね、金髪以外」と懐かしげに笑う。
「26歳にもなって未だアルバイトだし、大きい賞もあれからとれてないし、5年前と何も変わらないんだ」
俯き加減に口元だけくっと無理に持ち上げようとすると、ユタカくんは目の前にどら焼きを差し出した。
「すきなものは、ずっと変わらないけどね」
大好物をありがたく受け取ると、ユタカくんはそういえば、と何かを思い出したように呟く。
「『変わらないね』って言われるってことは、変わり続けている証拠なんだって」
どら焼きの袋の端を引っ張ると、ふわっと優しい甘さが香る。
鼻の奥がツンとして、目の縁まで涙が押し寄せてくるのをぐっとこらえた。
「横田は偉いよ」
文章を書き続けるのは、自分自身を溺れさせる行為なのかもしれない。言葉こそが、自分にとっては足枷になっているんじゃないか、とすら思っていた。
わたしは、わたしのすきなものを自分で否定してしまうところだった。そういうときにいつも助けてくれるのが、ユタカくんだった。
「半分ちょうだい」
「そういうとこだよ」
ふかふかのスポンジの真ん中に指でぐっと押す。割ったどら焼きの片方は極端に小さく、大きい方をユタカくんに渡した。
ユタカくんは受け取った半円の端っこを持って、さらにふたつに分ける。
4分の1の大きさになったどら焼きを見て、そういうところが変わらないね、と言おうと思ったけれど、口には出さない。
帰り道、空を仰ぐと、満月がひと粒の真珠のように白く光っていた。
文=ひらいめぐみ
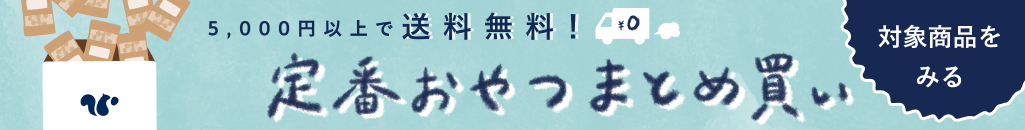
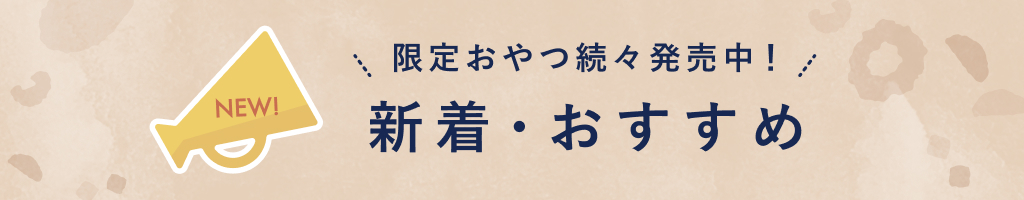
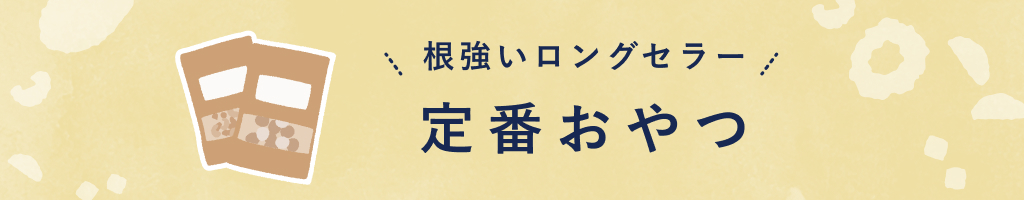
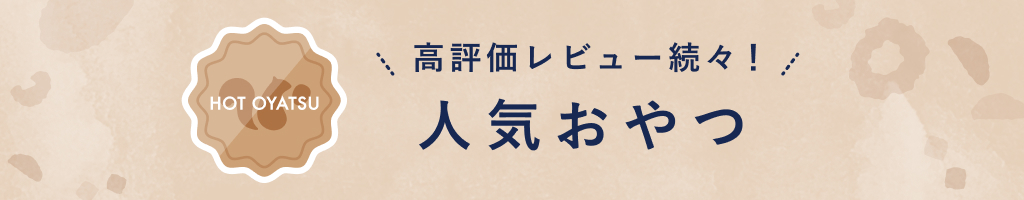
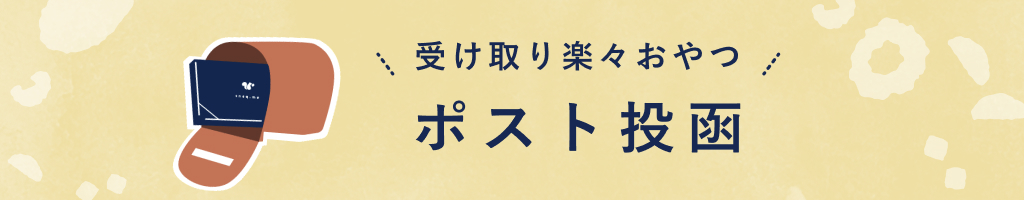

最新のよみもの
-

スナックミーの復刻おやつ特集🐿️
スナックミーは、今まで沢山の製造者様とおやつを作ってきました。おいしく仕上がっていたけれども泣く泣く販売がストップしてしまったものもあります。今回の特集では、過去に支持いただいていた人気のおやつをまたお届けできるようにしましたのでご紹介させていただきます。
-

春を先取る彩りおやつ特集🍓🌷
先週は東京にも雪が積もった驚きの週でしたが、2月に入りだんだんと春が近づいてきましたね。 スナックミーでは少し春を先取りして、彩りのあるおやつをご紹介します!
-

チョコおやつ特集 第二弾🍫
バレンタインも近づき、チョコレートおやつやバレンタイン限定イベントを沢山目にするようになりましたね。 スナックミーでも寒い冬の時期は沢山のチョコおやつを販売中・リクエスト受付中で、チョコおやつ特集第一段ではすべてをご紹介できなかったので、今回はチョコおやつ特集第二弾です! 自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントにいかがですか?



